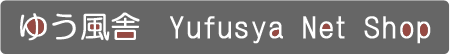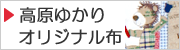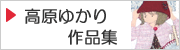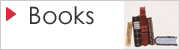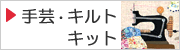読んで下さい
6月はもう目の前。
没後3年経っても、商魂たくましく、さまざまなマイケル関連のものが売り出されます。
もちろん、それでも、待ちわびているのですが…。
でも、本当に望んでいることは、一人でも多くの方に、彼の本当の姿を知ってほしいということです。
最近のオフィシャルサイトに彼の詩集、思索集[Dancing The Dream]についての話が書いてありました。
1992年6月。
もうその頃は世界中での人気と裏腹にアメリカでは(変人・奇人)と揶揄されていましたから、アメリカではなく、イギリスでの出版。
彼の事にしては、多くの注目を集めることもなく、ひっそりと出版されたようです。
現在でも和訳本は出ていないので、読んでいる人は少ないかもしれません。
でも、ありがたいことに、英語の堪能なファンがブログに全ての和訳を載せて下さっているのです。
それを読んでからは、アマゾンのカスタマーレビューにある、
「数ある追悼本、マイケル関連の本は何もいらない!この一冊だけで充分!」
とか
「読んでいると、胸がいっぱいになり『うわぁ〜!』と大声を出したくなり…」
というような感想がよく解りました。
長い文もあります。
でも、ちょっとずつでも紹介していきたいので、短めのものから載せさせていただこうと思います。
[bluemoon]さんという方の訳です。
[bluemoon]さん、ありがとう。
[DANCE OF LIFE―生命の踊り―]
「ぼくのそばにはいつも月がいる。
夜、柔らかな月の光がカーテンの隙間から差し込む。
ぼくには見なくてもわかるのだ。
冷たく青いエネルギーがベッドに降り注がれ、ぼくは起き上がる。
暗い廊下へ飛びだし、ドアを勢いよく開ける。
外に出るためにではなく、戻るために。
そして「月よ、ぼくはここだ!」と叫ぶ。
「ええ」と月が答える。「さあ、踊って。わたしたちのために」
その言葉を待つまでもなく、ぼくの体はとっくに動きだしている。
いつからだろう?自分でも思い出せない。ぼくの体は、いつも ひっきりなしに動いているのだ。
子供のころからぼくは、月に魅入られた変人のように、こうして彼女に話しかけてきた。
月だけじゃない。星たちもぼくを誘い、きらびやかな動きをぼくの目の前で見せてくれた。
彼らもまた踊りながら、分子をしなやかに震わせ、ぼくの炭素原子がそれに応じて飛び跳ねる。
両手を大きく広げ、海へ向かって歩いていくと、ぼくの体はまたしても踊り出す。
ぼくの中で月がゆるやかに、芝生に落ちる青白い影のように踊っている。
波のざわめきが地球の鼓動に聞こえ、踊りのテンポがいちだんと速くなる。
白い波頭のあいだをイルカが飛び跳ねる。
天まで届く大波が押し寄せた瞬間、イルカは今しも空へ舞い上がろうとする。
イルカの尾びれがきらめきながら弧を描き、波間にはプランクトンが光っている。
小魚の群れがぴちぴちと跳ね、月明かりのなかでまるで新しい星座のように銀色の光を放つ。
海が言う、「ああ!みんなが集まってくるわ」
片足を波に突っ込み、もう片方で波を蹴散らし、ぼくは海岸を走る。
ポンポンという小さな音が聞こえる。
数えきれないほどのカニが、驚いて穴の中へもぐりこむ音だ。
けれどもう、ぼくの足は止まらない。
つまさきで軽やかに、あるいは全速力で、ぼくは走る。
空をあおぐと、満点の星たちがいう。
「回っておくれ、速く!」
ぼくは笑い、頭を下げてポーズを決めると、思い切りワイルドにスピンをした。
こいつはぼくのお気に入りの踊りだ。
なぜって、これには秘密があるからだ。
速くスピンすればするほど、ぼくの心は穏やかになる。
外見はあくまでアクティブに、内面はあくまでも穏やかに、それがぼくの踊りだ。
ぼくは曲を作るのが大好きで、この踊りはいつまでも終わることのない、音のない音楽なのだ。
目には見えないけれど、静けさこそがぼくの本当の踊りだ。
それはいつもぼくのそばにいて、神から遣わされた振り付け師となって、指の一本一本に、つまさきに、祝福を与えてくれる。
ぼくは月も海もイルカのこともすっかり忘れ、それでいて彼らの喜びをこのうえなく、はっきりと感じとることができる。
あるいは星のように遠く、あるいは海辺の砂のように近く、彼らはきらびやかな光をふりまきながらぼくにせまる。
ぼくは愛に満ち、暖かなその世界に永遠に包まれる。
手を触れると、静寂のなかからたちまち光がこぼれだす。
光はぼくの心を震わせ、突き動かし、ぼくに気づかせてくれる。
この静寂、この光、この祝福こそがぼくの踊りなのだということを、すべての人々に示すのがぼくの宿命かのだ、と。
「さあ、早く与えて!」と光が言う。
ぼくは運命に従い、喜びをあらわす新しいステップ、新しい振り付けを生み出す。
そのとたん、ぼくは自分がどこにいるかを思い出し、丘の上へかけ戻る。
寝室の明かりがついたままになっている。
それを見て、ぼくはまた坂をかけおりる。
心臓が高鳴り、腕の力がぐったりと抜け、温かい血液が足にどくどくと流れていく。
もっとゆっくり踊ってくれと、細胞が訴える。
「少し歩こう」と彼らは言う。
「ちょっときつかったよ」と。
「いいとも」ぼくは笑い、歩調を緩める。
少し息を切らし、心地よい疲れを感じながらドアノブを回す。
ベッドにもぐりこむと、いつもの疑問がよみがえる。
ぼくたちが見ている夜空の星には、今はもう存在しないものがあるという。
星の光が地球へ届くまでには、何百年もの歳月がかかり、ぼくたちが今見ているのは、それらの星が輝いていた過去の光なのだと。
「すると、輝かなくなった星はそのあとどうなるんだろう?」と、ぼくは自分に問いかける。
「死んでしまうのだろうか」
「いいや、そんなことはない」と空から声が降ってくる。
「星は死なない。ただ、微笑んで宇宙の音楽に、生命の踊りに溶け込むだけさ」
目を閉じる前には思いつきもしなかったその考えを、ぼくはひどく気に入った。
ぼくは微笑を浮かべ、自分の肉体を音楽に溶け込ませたのだった。」